医師になるには?方法・流れを解説
本ページにはプロモーションが
含まれていることがあります

医師になりたい!と思ったら、どうすればいいのでしょうか?
小学・中学受験をして黙々と医学部を目指さなければ医師にはなれない、なんてことはありません。
高校生、大学生、社会人になってから医師を目指して勉強を始める人もたくさんいます。
しかし、早く準備を始めるに越したことはありません。
思い立ったが吉日。
このコラムでは、医師になるにはどうすればいいのか解説します。
医学部の合格を
目指している方へ
- 自分に合う教材を見つけたい
- 無料で試験勉強をはじめてみたい
アガルートメディカルの医学部入試講座を
無料体験してみませんか?
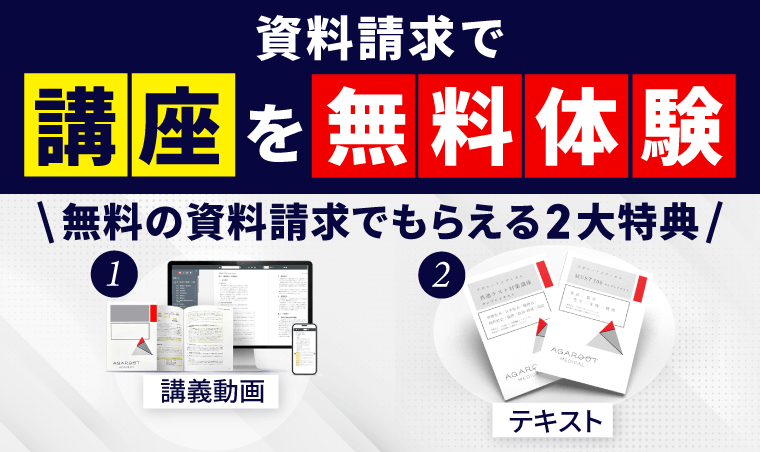
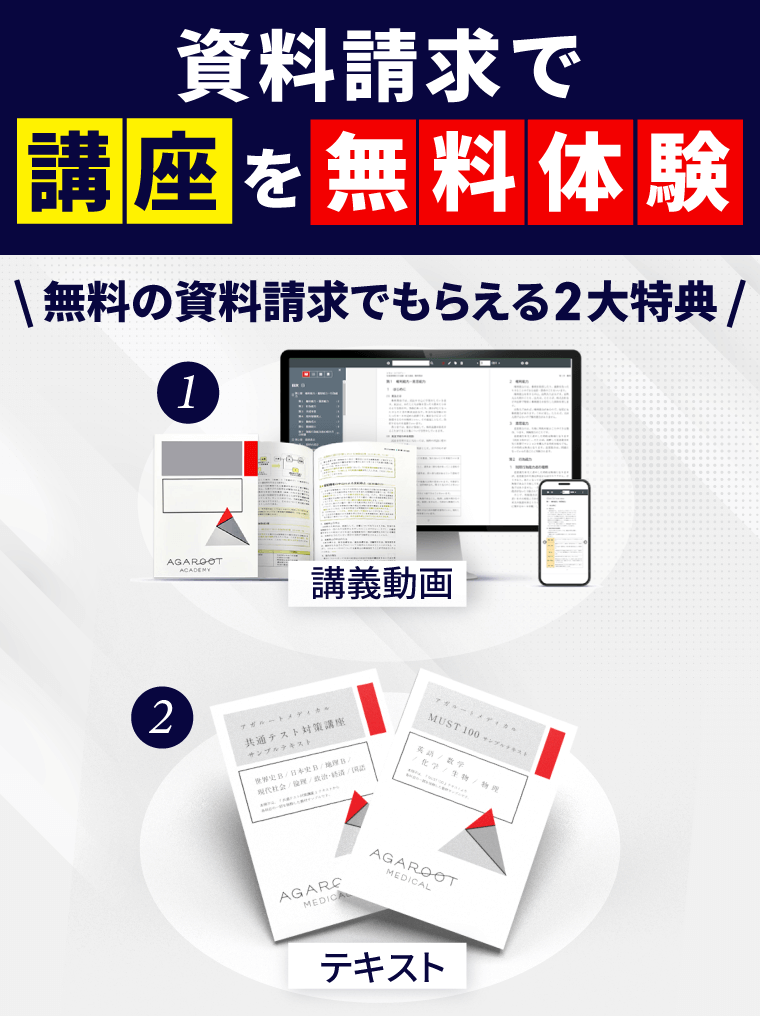
約10時間分の英語・数学・化学・生物・物理講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!医学部入試対策のフルカラーテキスト
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る医師になるには
医師になって、ある程度の力量を身に着けるまでの流れは以下のような感じです。
①医学部に入学して6年間教育を受ける
②医師国家試験に合格する
③初期研修(臨床研修)を2年間受ける
④後期研修を3~4年間受ける
まず、大学の医学部に入学し、6年間の所定のカリキュラムを完了して単位をすべて取得する必要があります。
医学部の卒業見込み、または卒業によって医師国家試験受験資格を得られます。
医師国家試験合格で医師として認められたことになります。
ただし、これだけではまだまだ診療能力は身についておらず、医師としてある程度独り立ちするためには、初期研修(臨床研修)を2年間、後期研修を3~4年受けて各種専門医を目指すことになります。
初期研修(臨床研修)で複数の診療科をローテートして自分の診療科を選択し、後期研修で研鑽を積みます。
次の章以降で1つずつ解説します。
①医学部に入学する
医師になるにはまず、日本の大学の医学部に入学して医学の正規の課程を修めて卒業するのが一般的です。
ただし、一度大学を卒業するなどしてから学士入学をしたり、他学部から編入する形で医学部に入学したりすることも大学によっては可能です。
入学後は、語学を含めた一般教養、基礎医学、臨床医学、臨床実習と様々なカリキュラムをすべてクリアする必要があり、もし試験に不合格だった場合には追試験が必要になります。
すべての単位を取得したら、いよいよ卒業試験にいどみます。
卒業試験をクリアし、医学部の卒業見込み、または卒業によって医師国家試験受験資格を得ることができます。
医学部のカリキュラムは他学部に比べてかなり科目数が多く、夏休みなどの期間も短いのが特徴です。
なお、外国の医学校を卒業し、又は外国において医師免許を得た人が日本で医師国家試験を受けるためには、審査を受けて医師国家試験受験資格認定を受ける必要があります。
②医師国家試験に合格する
医師国家試験のスケジュールは年によって少しずつ変わるのですが、例年だいたい2月頃に実施されます。
※2023年の医師国家試験(第117回)は、2月4日(土)と2月5日(日)の2日間になります。
将来何科の医師になるかは関係なくすべての試験問題を受験する必要があり、過酷な試験です。
例えば第115回医師国家試験では、A問題からF問題まで合計400問が出題されました。
合格率は91.4%でしたから決して狭き門というわけではありませんが、必修問題,一般問題・臨床問題それぞれに合格基準が設けられており、それぞれ合格基準をクリアしなければなりませんでした。
また、禁忌肢問題と言って、これを4問以上間違えると、他の問題でいくら正答率が高くても不合格となるという問題が含まれているので、注意が必要です。
患者さんにとって重大な悪影響を及ぼす医療行為や法律に反することがこの禁忌肢になっています。
「選んだら絶対ダメ」な選択肢です。
厚生労働省のHPで第115回医師国家試験の問題と正答が公開されていますので、一度、目を通してみて下さいね。
③臨床研修を2年間受ける
医師国家試験に合格した後、2年以上の研修期間が必修になっています。
これを初期研修(臨床研修)と言います。
この期間に、プライマリ・ケア(病気の初期診療)の基本的な診療能力(態度・技能・知識)を身につけるために研鑽を積みます。
また、研修希望者と臨床研修を行う病院の双方の希望順位が高い順にコンピューターで組み合わせを決定するシステムを研修医マッチングと言います。
自分に合った研修病院・プログラムを選択することが重要で、学生のうちから情報収集が必要です。
2020年度からは、初期研修では内科・救急・外科・小児科・産婦人科・精神科・地域医療が必須となっており、他に診療科を選ぶことができます。
また、一般外来における研修も必修とされました。
数か月ごとに次の診療科にローテートしなければならないので、慣れたと思ったらすぐ次の科に移ることになります。
また、ただ研修を受けるだけではなく、診療各科ごとに「研修医評価表」によって、医師としての基本的価値難に関する評価、資質・能力に関する評価、基本亭診療業務に関する評価を受けなければなりません。
④後期研修を受ける
基本的には内科専門医や外科専門医など各専門医の取得を目的とするのが後期研修です。
必須ではありませんが、一般的には医学部卒業後3~6年目、初期研修後に専門医を取得するまでの期間にあたります。
2018年4月に始まった新専門医制度においては、専門研修プログラムを受けて専門医を取得する時期で、以前は「後期研修医」と言っていましたが、新専門医制度においては「専攻医」と呼びます。
必修の研修科目が決められていた初期研修医とは違い、後期研修の期間は自分が選択した診療科の専門医取得を目指します。
この後期研修の時期には、現場の即戦力として活躍することが期待されます。
外科専門医など基本領域の専門医を取得した後にさらにサブスペシャルティ専門医(消化器外科専門医など)を目指すことになります。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
医師になるのは少々たいへんですが、コロナ禍に医療体制の重要性がフォーカスされましたよね。
やりがいのある仕事です。
また、医学は日進月歩なので医師になってからも勉強が必要です。
でも、医師になるために身に着けた知識のみならず、勉強方法・習慣は医師になってからも役に立ちます。
医師になるという目標に向けてコツコツ頑張っていけた人なら、医師になってからも十分やっていけます。
「継続は力なり」で、頑張りましょう。
関連コラム:医学部受験をする方へ、基礎データを紹介!
医学部の合格を
目指している方へ
- 医学部に合格できるか不安
- 勉強をどう進めて良いかわからない
- 勉強時間も費用も抑えたい
アガルートメディカルの医学部入試講座を
無料体験してみませんか?

追加購入不要!これだけで合格できるカリキュラム
充実のサポート体制だから安心
合格特典付き!
現役難関医学部生によるコーチング付!
4月30日までの申込で20%OFF!
▶医学部入試講座を見る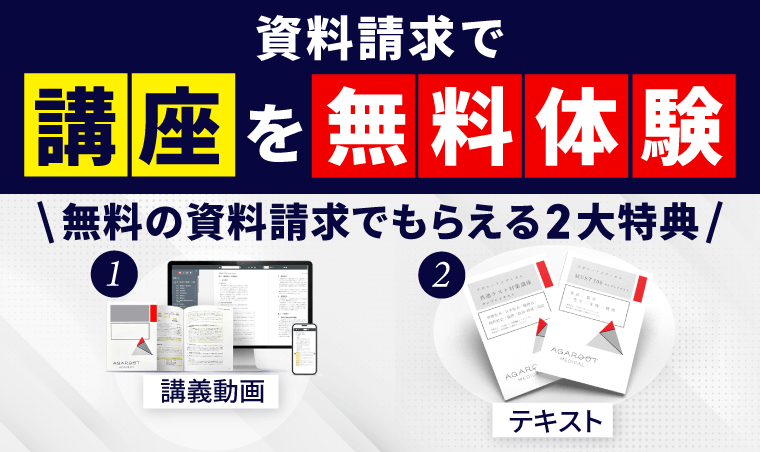
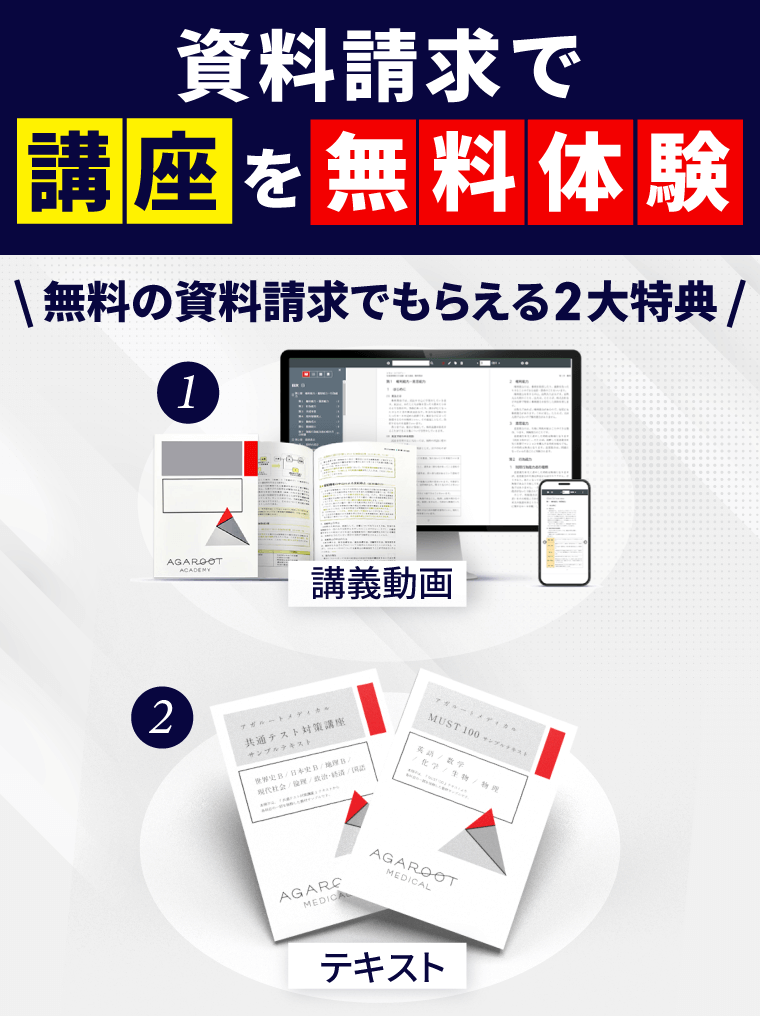
約10時間分の英語・数学・化学・生物・物理講義が20日間見放題!
実際に勉強できる!医学部入試対策のフルカラーテキスト
1分で簡単!無料
▶資料請求して特典を受け取る
この記事の監修者 Melon
京都大学医学部卒業
京都大学大学院医学研究科博士課程修了
医師・医学博士
日本外科学会専門医・指導医
日本消化器外科学会専門医・指導医
米国外科学会フェロー(FACS)
大学・看護学校の教員としての勤務歴や、医学部受験生を対象にした指導歴など
幅広い指導経験を持つ
若手医師などからの質問を随時引き受け、
大手医療メディアで回答を公開している。




